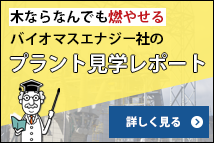sponsored by バイオマスエナジー社
- 木くずの再利用
- 木材のカスケード利用
- 製材を安定供給するために必要なこと
- 【特集】木材の最新リサイクル法 木質バイオマスとは
- 戻る
- 【特集】木材の最新リサイクル法 木質バイオマスとは_TOP
- 木質バイオマスのガイドラインとは?
- 小型木質バイオマス発電のメリット・デメリット
- バイオマスプラントとはどんな設備?
- バイオマス産業都市とは?
- 国内クレジット制度とは?バイオマス発電との関係も解説
- 木質バイオマス発電で発生する灰の処理方法
- バイオマス発電の
燃料調達方法・買取価格 - バイオマス発電の発電効率は?他の再生可能エネルギーと比較
- バイオマス発電事業を成功させるポイント
- バイオマス発電で想定されるトラブルとは
- バイオマス発電所の熱活用・熱利用
- 放射能汚染された木質燃料の危険性について
- 木質バイオマス発電は林業にとってプラスに働くのか?
- 地域活性化にはバイオマスが欠かせない?
- 森林経営管理制度とバイオマスの関係とは?
- 木質バイオマスの必要性とは
- バイオマス事業の将来性について
- 木質バイオマス利用施設に関連する補助金
- 小規模木質バイオマス発電の発電コストはどれくらい?
- 木質ガス化システムの仕組みとは?
- 直接燃焼発電とガス化発電の違いとは
- 木質バイオマスのメリット・デメリットとは
- 木くずが原因で起こった裁判
- バイオマス発電を事業化するには
- バイオマス発電の仕組みや特徴とは
- バイオマスボイラーを導入した場合のコスト
- バイオマスボイラー導入に関する注意点と法律
- 木質バイオマスの燃料
- 木質バイオマスの補助金
- 木質バイオマスの導入事例
- 木質バイオマスのプラント見学レポート
- 木質バイオマスのセミナー情報
- 木質バイオマスの失敗事例
- 木質バイオマス発電所の
保守・メンテナンス施策 - バイオマス発電の燃料を安定調達するために
- バイオマス用語集
- 木材リサイクル・バイオマスのコラムまとめ
- 戻る
- 木材リサイクル・バイオマスのコラムまとめ_TOP
- 産業廃棄物としての木くずの処理方法とは?
- クリーンウッド法とは?リサイクルとの関連性とは?
- リサイクルとアップサイクルの違いとは?
- 端材と廃材の違いとは?
- 脱炭素社会を目指す木材利用の可能性と課題について
- 木材利用によるCO2削減と
木質バイオマスとしての活用 - 産業廃棄物のリサイクルは必要?
どんなメリットがある? - 木材チップ・木質チップの含水率について知る
- 木質チップの品質規格について
- 廃棄物系バイオマスの利活用を考える
- ウッドプラスチックとは?廃木材のリサイクル事例について
- PCB廃棄物の木材の処理方法は?リサイクルはできる?
- 木質バイオマスにおける
固定価格買取(FIT買取 ) - 竹がバイオマス燃料に不向きな理由と近年の研究成果
- バイオマス発電投資をする前に考えるべきこと
- 価値を生む林地残材!
- 広い森林面積を持つ日本
- 産業廃棄物を処理するコストを削減するには
- エネルギー基本計画とは
- 固定価格買取制度(FIT制度)とは?
- 「地域内エコシステム」とは?
- バイオマス発電は輸入燃料頼み?人手不足の理由とは
- バイオマス発電でFITが見直しによりどうなるの?
- バイオマスビジネス参入するならどんな事業モデルがある?
- バイオマス発電とバイオガス発電の違いとは?
- バイオマス発電の魅力とは?
- エシカル消費ってなに?
- バイオマス発電とカーボンニュートラルの仕組み
- バイオマスとSDGs
- バイオマス活用推進基本計画とは?
- 木質バイオマスに使用されるボイラーの種類
- 木質バイオマス発電と熱電併給について
- 【エリア別】木質バイオマスの導入事例
- 戻る
- 【エリア別】木質バイオマスの導入事例_TOP
- 沖縄県の木質バイオマス導入事例
- 神奈川県の木質バイオマス導入事例
- 石川県の木質バイオマス導入事例
- 山口県の木質バイオマス導入事例
- 茨城県の木質バイオマス導入事例
- 宮城県の木質バイオマス導入事例
- 千葉県の木質バイオマス導入事例
- 埼玉県の木質バイオマス導入事例
- 兵庫県の木質バイオマス導入事例
- 滋賀県の木質バイオマス導入事例
- 大阪府の木質バイオマス導入事例
- 京都府の木質バイオマス導入事例
- 鳥取県の木質バイオマス導入事例
- 和歌山県の木質バイオマス導入事例
- 山梨県の木質バイオマス導入事例
- 群馬県の木質バイオマス導入事例
- 富山県の木質バイオマス導入事例
- 三重県の木質バイオマス導入事例
- 愛知県の木質バイオマス導入事例
- 新潟の木質バイオマス導入事例
- 静岡県の木質バイオマス導入事例
- 岐阜県の木質バイオマス導入事例
- 長野県の木質バイオマス導入事例
- 栃木の木質バイオマス導入事例
- 福島県の木質バイオマス導入事例
- 山形県の木質バイオマス導入事例
- 青森県の木質バイオマス導入事例
- 秋田県の木質バイオマス導入事例
- 香川県の木質バイオマス導入事例
- 徳島県の木質バイオマス導入事例
- 広島県の木質バイオマス導入事例
- 岡山県の木質バイオマス導入事例
- 鹿児島県の木質バイオマス導入事例
- 熊本県の木質バイオマス導入事例
- 愛媛県の木質バイオマス導入事例
- 大分県の木質バイオマス導入事例
- 長崎県の木質バイオマス導入事例
- 佐賀県の木質バイオマス導入事例
- 福岡県の木質バイオマス導入事例
- 岩手県の木質バイオマス導入事例
- 北海道の木質バイオマス導入事例
- 宮崎県の木質バイオマス導入事例
- 島根県の木質バイオマス導入事例
- 高知県の木質バイオマス導入事例
- 奈良県の木質バイオマス導入事例
- 福井県の木質バイオマス導入事例
- 東京都の木質バイオマス導入事例
- 取材協力・運営者情報
バイオマス事業の将来性について
地球環境にやさしいカーボンニュートラルなバイオマス。バイオマス燃料を用いた発電事業は、近年、注目を集めつつあります。けれども、この事業の将来性を考慮したとき、解決すべき問題のは事実。このページでは、バイオマス事業の収益特性や地域との連携の重要性の観点から現状の問題をみていきます。
バイオマス事業が抱える問題点とは
廃棄物処理の状況を改善するためのひとつの方法として取り組まれてきた「バイオマスエネルギー事業」。けれども、その後、政府がFIT制度をスタートさせ、きちんと収益を出すことが見込める事業として認識されるようになりました。ただし、この制度は時限的なものであり、やがてはFIT制度の電気買取は終了するでしょう。
そのため、現段階からFIT制度への依存度を低くしていき、持続可能なバイオマス事業として確立させる必要があります。現在の状態のままでは、バイオマス事業単体での経済的な面における効果は大きくありません。そのため、地域社会にとって欠かせない存在の事業へと成長していくことが長期的に持続させるための条件だといえます。
収益を出し続けるための事業構造
バイオマスエネルギー事業を将来性のあるものとするためには、事業の収益特性を理解しておきたいところです。本サイトでは木質系のバイオマスを主軸に扱っていますが、木質バイオマスの収益のしくみをより本質的に理解するためにも、もう一方の湿潤バイオマスについての収益特性について説明していきます。同じバイオマスエネルギー事業に属しているわけですから、比較しつつ特性の違いを確認してください。
木質系バイオマス事業の場合
電力生産コストが高い
現行のFIT制度に大きく依存している面が否めません。その最も大きな理由は、コストの高さです。それに加えて、燃料を大量に調達するのが難しいといった問題もあります。そのため、バイオマス発電の場合、調達コストだけで石炭火力発電のトータルのコストを上回ってしまう場合すらあります。
コストを少しでも抑えて運転するために有効なのは、発電効率をアップさせることです。基本的には、発電規模が大きくなっていくにつれ発電効率がアップするため、おのずと発電にかかるコストが下がっていくわけです。そのためには、先述のとおり、燃料の大量調達を安定的にかつスムーズに行えることが前提となります。
バイオマス発電の規模とコスト
ここで、発電規模と発電効率の関係がどのようになっているのか、数字でみていきましょう。ある試算モデルでは、発電規模が1,500キロワットの場合、発電効率は16%です。一方、発電規模が5700キロワットの場合、発電効率は23%まで上昇します。「発電効率が低い=発電コストが高い」という関係が成り立つので、前者の場合はよりコストがかかっていることになります。
湿潤系バイオマス事業の場合
木質系バイオマスとの違い
木質系バイオマスが基本的に木材由来であるのに対し、湿潤系バイオマスは畜産農業由来です。収益も、木質系が電力の販売によるものであるのに対し、湿潤系(のメタン発酵事業)では廃棄物処理自体が多くを占めています。後者の場合もエネルギー販売によって収益をあげてはいますが、かならずしもメインではありません。
木質系バイオマス事業と湿潤系バイオマス事業とでは、収益特性が対照的であることがわかります。FIT制度の影響で売電事業に以前よりは力を入れるようにはなったものの、湿潤系バイオマス事業の主な社会的役割といえるのは、「廃棄物処理」のほうです。
湿潤系バイオマス事業の支出と収入
湿潤系バイオマス事業における発電でも、規模が大きくなればなるほど、収入も増加していきます。支出は穏やかな増加のみ。そのため、廃棄物処理などをメインとする事業内容であれば、十分にビジネスとして成立する収益を見込めます。
また、湿潤系バイオマスの機能である廃棄物処理機能は、地域にとって持続的に必要であるため、FIT制度の有無に関わらず事業成立するように計画することが重要となります。
廃棄物処理は、地域において、当然これからも必要不可欠。長期的かつ持続的な需要があるといえるわけです。そのため、FITの有無にあまり左右されることなく、社会的役割を中心にすえてビジネスを構築していけるかどうかが成功のカギとなります。
地域との連携の重要性
木質バイオマス事業をビジネスとして成立させるためには、やはり単体としてではなく、地域との連携が必要不可欠。まずは地域社会、そして地域の産業との信頼関係をきずくことが大切です。信頼関係があれば、地域産業と上手に連携をはかり、協力体制を築けるはずです。
そうすることで、木質バイオマス事業で問題となりがちな「安定的な燃料調達方法」や「燃料調達のコスト」の改善も期待できます。さらに、生産したエネルギーの供給先の創出も比較的スムーズになるでしょう。地域との協力体制のもと、バイオマス事業の将来性や発展の可能性を感じられるようになり、力の入れようもさらにかわってきます。
将来性のある木質系バイオマス事業とは
協力体制をはかるために必要な検討
木質系バイオマス事業について、事業者と地域が合意形成を進める中で、きちんと検討すべきポイントは大きく分けて2つあります。
ひとつは、「地域内にある森林を将来的にどのように取り扱うのか」という問題です。両者が森林の現状に関して共通の認識をもった上で、今後の素材生産量や素材生産費用などの移り変わりなどの分析を行うことは、ビジネスを行う際には大変重要です。
もうひとつは、「地域における産業のあり方」です。産業の現状を理解し、と今後のあり方が定まれば、将来のビジネス展開についての議論を進められるようになります。どのくらいの熱需要が見込まれるか、あるいは木材資源の出荷先の創出や選択など、議論すべきことはたくさんあります。
具体例
比較的高級な木材加工製品を地域産業として力をいれていく場合を考えてみましょう。まず予想されるのが、効率性を重視した工場の大規模化です。また、バイオマス発電事業も、工場の規模の変化に沿って乾燥熱などの需要拡大を検討されます。こういった流れを考えると、事業者と地域内の他の複数の事業や産業との密接な連携の重要性がより一層強く実感されます。

https://www.bme.co.jp/wp/
木を選ばない
唯一無二のプラントを持つ
バイオマスエナジー社
木を原料に温風や水蒸気、バイオマスガスといった新たなエネルギーとしてリサイクルする画期的手法が、木質バイオマス。しかし、これまでバイオマスを燃やすプラントには燃料の制限があり、使いたい木材に対応できないというものばかりでした。
そうしたなかで、どんな木でも燃やせるプラントを誕生させたのが、バイオマスエナジー社です。当サイトでは、唯一無二のプラントを持つバイオマスエナジー社(2019年7月現在)に取材協力を依頼。実際にどんなプラントなのか、そしてコスト削減はどれくらいか。現地取材しレポートにまとめたので、ぜひご覧ください。