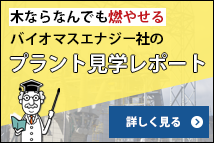sponsored by バイオマスエナジー社
- 木くずの再利用
- 木材のカスケード利用
- 製材を安定供給するために必要なこと
- 【特集】木材の最新リサイクル法 木質バイオマスとは
- 戻る
- 【特集】木材の最新リサイクル法 木質バイオマスとは_TOP
- 木質バイオマスのガイドラインとは?
- 小型木質バイオマス発電のメリット・デメリット
- バイオマスプラントとはどんな設備?
- バイオマス産業都市とは?
- 国内クレジット制度とは?バイオマス発電との関係も解説
- 木質バイオマス発電で発生する灰の処理方法
- バイオマス発電の
燃料調達方法・買取価格 - バイオマス発電の発電効率は?他の再生可能エネルギーと比較
- バイオマス発電事業を成功させるポイント
- バイオマス発電で想定されるトラブルとは
- バイオマス発電所の熱活用・熱利用
- 放射能汚染された木質燃料の危険性について
- 木質バイオマス発電は林業にとってプラスに働くのか?
- 地域活性化にはバイオマスが欠かせない?
- 森林経営管理制度とバイオマスの関係とは?
- 木質バイオマスの必要性とは
- バイオマス事業の将来性について
- 木質バイオマス利用施設に関連する補助金
- 小規模木質バイオマス発電の発電コストはどれくらい?
- 木質ガス化システムの仕組みとは?
- 直接燃焼発電とガス化発電の違いとは
- 木質バイオマスのメリット・デメリットとは
- 木くずが原因で起こった裁判
- バイオマス発電を事業化するには
- バイオマス発電の仕組みや特徴とは
- バイオマスボイラーを導入した場合のコスト
- バイオマスボイラー導入に関する注意点と法律
- 木質バイオマスの燃料
- 木質バイオマスの補助金
- 木質バイオマスの導入事例
- 木質バイオマスのプラント見学レポート
- 木質バイオマスのセミナー情報
- 木質バイオマスの失敗事例
- 木質バイオマス発電所の
保守・メンテナンス施策 - バイオマス発電の燃料を安定調達するために
- バイオマス用語集
- 木材リサイクル・バイオマスのコラムまとめ
- 戻る
- 木材リサイクル・バイオマスのコラムまとめ_TOP
- 木質チップとペレットの違いとは?
- 産業廃棄物としての木くずの処理方法とは?
- クリーンウッド法とは?リサイクルとの関連性とは?
- リサイクルとアップサイクルの違いとは?
- 端材と廃材の違いとは?
- 脱炭素社会を目指す木材利用の可能性と課題について
- 木材利用によるCO2削減と
木質バイオマスとしての活用 - 産業廃棄物のリサイクルは必要?
どんなメリットがある? - 木材チップ・木質チップの含水率について知る
- 木質チップの品質規格について
- 廃棄物系バイオマスの利活用を考える
- ウッドプラスチックとは?廃木材のリサイクル事例について
- PCB廃棄物の木材の処理方法は?リサイクルはできる?
- 木質バイオマスにおける
固定価格買取(FIT買取 ) - 竹がバイオマス燃料に不向きな理由と近年の研究成果
- バイオマス発電投資をする前に考えるべきこと
- 価値を生む林地残材!
- 広い森林面積を持つ日本
- 産業廃棄物を処理するコストを削減するには
- エネルギー基本計画とは
- 固定価格買取制度(FIT制度)とは?
- 「地域内エコシステム」とは?
- バイオマス発電は輸入燃料頼み?人手不足の理由とは
- バイオマス発電でFITが見直しによりどうなるの?
- バイオマスビジネス参入するならどんな事業モデルがある?
- バイオマス発電とバイオガス発電の違いとは?
- バイオマス発電の魅力とは?
- エシカル消費ってなに?
- バイオマス発電とカーボンニュートラルの仕組み
- バイオマスとSDGs
- バイオマス活用推進基本計画とは?
- 木質バイオマスに使用されるボイラーの種類
- 木質バイオマス発電と熱電併給について
- 【エリア別】木質バイオマスの導入事例
- 戻る
- 【エリア別】木質バイオマスの導入事例_TOP
- 沖縄県の木質バイオマス導入事例
- 神奈川県の木質バイオマス導入事例
- 石川県の木質バイオマス導入事例
- 山口県の木質バイオマス導入事例
- 茨城県の木質バイオマス導入事例
- 宮城県の木質バイオマス導入事例
- 千葉県の木質バイオマス導入事例
- 埼玉県の木質バイオマス導入事例
- 兵庫県の木質バイオマス導入事例
- 滋賀県の木質バイオマス導入事例
- 大阪府の木質バイオマス導入事例
- 京都府の木質バイオマス導入事例
- 鳥取県の木質バイオマス導入事例
- 和歌山県の木質バイオマス導入事例
- 山梨県の木質バイオマス導入事例
- 群馬県の木質バイオマス導入事例
- 富山県の木質バイオマス導入事例
- 三重県の木質バイオマス導入事例
- 愛知県の木質バイオマス導入事例
- 新潟の木質バイオマス導入事例
- 静岡県の木質バイオマス導入事例
- 岐阜県の木質バイオマス導入事例
- 長野県の木質バイオマス導入事例
- 栃木の木質バイオマス導入事例
- 福島県の木質バイオマス導入事例
- 山形県の木質バイオマス導入事例
- 青森県の木質バイオマス導入事例
- 秋田県の木質バイオマス導入事例
- 香川県の木質バイオマス導入事例
- 徳島県の木質バイオマス導入事例
- 広島県の木質バイオマス導入事例
- 岡山県の木質バイオマス導入事例
- 鹿児島県の木質バイオマス導入事例
- 熊本県の木質バイオマス導入事例
- 愛媛県の木質バイオマス導入事例
- 大分県の木質バイオマス導入事例
- 長崎県の木質バイオマス導入事例
- 佐賀県の木質バイオマス導入事例
- 福岡県の木質バイオマス導入事例
- 岩手県の木質バイオマス導入事例
- 北海道の木質バイオマス導入事例
- 宮崎県の木質バイオマス導入事例
- 島根県の木質バイオマス導入事例
- 高知県の木質バイオマス導入事例
- 奈良県の木質バイオマス導入事例
- 福井県の木質バイオマス導入事例
- 東京都の木質バイオマス導入事例
- 取材協力・運営者情報
木質バイオマス発電で発生する灰の処理方法
木質バイオマス発電において発生する灰を、適切に処理することは重要です。発生する灰の種類と、それぞれの処理方法について、詳しく解説します。
木質バイオマス発電の灰の種類
木質バイオマス発電では、木質チップなどのバイオマスをボイラーで大量に燃焼させます。ボイラー内やフィルター部分などに灰が発生し、廃棄物として蓄積されるてしまうのです。
木質バイオマス発電の灰は、発生する場所によって、主に以下の2種類があります。
燃焼炉で発生する「主灰」
「主灰」とは、燃焼炉の燃えカスとして発生する灰のことです。木質バイオマス発電においては、ボイラーの火床部分に蓄積されます。
燃焼によって飛び散った灰ではなく、炉底に落下した灰が「主灰」です。「ボトムアッシュ」とも呼ばれます。
フィルターなどで発生する「飛灰」
ボイラー内の燃焼によって舞い上がった灰が「飛灰」です。「フライアッシュ」とも呼ばれます。
飛灰は、そのまま煙突から出てしまうのではなく、フィルターで集められ、外部への飛散されないように対策されています。多くの木質バイオマス発電施設では、ボイラーの排気が「マルチサイクロン」と呼ばれる集塵装置を通過した後、「バグフィルター」を通過して、煙突から外気に放出されます。
マルチサイクロンで集められた灰を「サイクロン飛灰」、バグフィルターで集められた灰を「フィルター飛灰」と呼びます。
木質バイオマスのボイラー灰の処理方法
木質バイオマス発電で発生する灰は、どのように処理すればよいのでしょうか。
産業廃棄物として処理する
木質バイオマス発電で発生する灰には、鉛やカドミウム、水銀などが含まれていることがあります。そのような重金属が含まれる灰は、産業廃棄物として処理するのが一般的です。
これは、ボイラーの燃焼効率を高めるために石炭を混合して燃焼させた場合や、建築廃材等に由来する木質バイオマスの場合があるため、灰に多くの有害物質が含まれているのです。また、産業廃棄物ですので、法律に従った方法で廃棄する必要があります。
灰の種類によって処理方法が異なる
木質バイオマスのボイラー灰は、「主灰」と「飛灰」で処理方法が異なるという点に注意しましょう。
産業廃棄物の処理方法は、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)によって定められており、主灰は「燃え殻」、飛灰は「ばいじん」に分類されます。
いずれの灰も、運搬の際に有害物質が飛散することを防ぐために、コンクリートなどで固めてから処理する必要があります。
リサイクルの道もある
木質バイオマス発電によって発生する灰を、捨てる場合は「産業廃棄物」ですが、適切に加工してリサイクルすれば廃棄物ではなくなり、資源の有効活用につながります。
実際、木質バイオマス発電によるボイラー灰から抽出した成分を、肥料として使うなどのリサイクル方法が検討されているのです。セメントの原料として利用されることもあります。
木質バイオマス発電施設は、できるだけ廃棄物を減らす工夫をしながら稼働させることで、ゴミ問題にも配慮しながら運用することが大切です。

https://www.bme.co.jp/wp/
木を選ばない
唯一無二のプラントを持つ
バイオマスエナジー社
木を原料に温風や水蒸気、バイオマスガスといった新たなエネルギーとしてリサイクルする画期的手法が、木質バイオマス。しかし、これまでバイオマスを燃やすプラントには燃料の制限があり、使いたい木材に対応できないというものばかりでした。
そうしたなかで、どんな木でも燃やせるプラントを誕生させたのが、バイオマスエナジー社です。当サイトでは、唯一無二のプラントを持つバイオマスエナジー社(2019年7月現在)に取材協力を依頼。実際にどんなプラントなのか、そしてコスト削減はどれくらいか。現地取材しレポートにまとめたので、ぜひご覧ください。