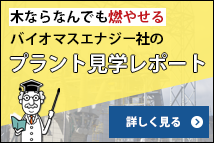sponsored by バイオマスエナジー社
- 木くずの再利用
- 木材のカスケード利用
- 製材を安定供給するために必要なこと
- 【特集】木材の最新リサイクル法 木質バイオマスとは
- 戻る
- 【特集】木材の最新リサイクル法 木質バイオマスとは_TOP
- 木質バイオマスのガイドラインとは?
- 小型木質バイオマス発電のメリット・デメリット
- バイオマスプラントとはどんな設備?
- バイオマス産業都市とは?
- 国内クレジット制度とは?バイオマス発電との関係も解説
- 木質バイオマス発電で発生する灰の処理方法
- バイオマス発電の
燃料調達方法・買取価格 - バイオマス発電の発電効率は?他の再生可能エネルギーと比較
- バイオマス発電事業を成功させるポイント
- バイオマス発電で想定されるトラブルとは
- バイオマス発電所の熱活用・熱利用
- 放射能汚染された木質燃料の危険性について
- 木質バイオマス発電は林業にとってプラスに働くのか?
- 地域活性化にはバイオマスが欠かせない?
- 森林経営管理制度とバイオマスの関係とは?
- 木質バイオマスの必要性とは
- バイオマス事業の将来性について
- 木質バイオマス利用施設に関連する補助金
- 小規模木質バイオマス発電の発電コストはどれくらい?
- 木質ガス化システムの仕組みとは?
- 直接燃焼発電とガス化発電の違いとは
- 木質バイオマスのメリット・デメリットとは
- 木くずが原因で起こった裁判
- バイオマス発電を事業化するには
- バイオマス発電の仕組みや特徴とは
- バイオマスボイラーを導入した場合のコスト
- バイオマスボイラー導入に関する注意点と法律
- 木質バイオマスの燃料
- 木質バイオマスの補助金
- 木質バイオマスの導入事例
- 木質バイオマスのプラント見学レポート
- 木質バイオマスのセミナー情報
- 木質バイオマスの失敗事例
- 木質バイオマス発電所の
保守・メンテナンス施策 - バイオマス発電の燃料を安定調達するために
- バイオマス用語集
- 木材リサイクル・バイオマスのコラムまとめ
- 戻る
- 木材リサイクル・バイオマスのコラムまとめ_TOP
- 木質チップとペレットの違いとは?
- 産業廃棄物としての木くずの処理方法とは?
- クリーンウッド法とは?リサイクルとの関連性とは?
- リサイクルとアップサイクルの違いとは?
- 端材と廃材の違いとは?
- 脱炭素社会を目指す木材利用の可能性と課題について
- 木材利用によるCO2削減と
木質バイオマスとしての活用 - 産業廃棄物のリサイクルは必要?
どんなメリットがある? - 木材チップ・木質チップの含水率について知る
- 木質チップの品質規格について
- 廃棄物系バイオマスの利活用を考える
- ウッドプラスチックとは?廃木材のリサイクル事例について
- PCB廃棄物の木材の処理方法は?リサイクルはできる?
- 木質バイオマスにおける
固定価格買取(FIT買取 ) - 竹がバイオマス燃料に不向きな理由と近年の研究成果
- バイオマス発電投資をする前に考えるべきこと
- 価値を生む林地残材!
- 広い森林面積を持つ日本
- 産業廃棄物を処理するコストを削減するには
- エネルギー基本計画とは
- 固定価格買取制度(FIT制度)とは?
- 「地域内エコシステム」とは?
- バイオマス発電は輸入燃料頼み?人手不足の理由とは
- バイオマス発電でFITが見直しによりどうなるの?
- バイオマスビジネス参入するならどんな事業モデルがある?
- バイオマス発電とバイオガス発電の違いとは?
- バイオマス発電の魅力とは?
- エシカル消費ってなに?
- バイオマス発電とカーボンニュートラルの仕組み
- バイオマスとSDGs
- バイオマス活用推進基本計画とは?
- 木質バイオマスに使用されるボイラーの種類
- 木質バイオマス発電と熱電併給について
- 【エリア別】木質バイオマスの導入事例
- 戻る
- 【エリア別】木質バイオマスの導入事例_TOP
- 沖縄県の木質バイオマス導入事例
- 神奈川県の木質バイオマス導入事例
- 石川県の木質バイオマス導入事例
- 山口県の木質バイオマス導入事例
- 茨城県の木質バイオマス導入事例
- 宮城県の木質バイオマス導入事例
- 千葉県の木質バイオマス導入事例
- 埼玉県の木質バイオマス導入事例
- 兵庫県の木質バイオマス導入事例
- 滋賀県の木質バイオマス導入事例
- 大阪府の木質バイオマス導入事例
- 京都府の木質バイオマス導入事例
- 鳥取県の木質バイオマス導入事例
- 和歌山県の木質バイオマス導入事例
- 山梨県の木質バイオマス導入事例
- 群馬県の木質バイオマス導入事例
- 富山県の木質バイオマス導入事例
- 三重県の木質バイオマス導入事例
- 愛知県の木質バイオマス導入事例
- 新潟の木質バイオマス導入事例
- 静岡県の木質バイオマス導入事例
- 岐阜県の木質バイオマス導入事例
- 長野県の木質バイオマス導入事例
- 栃木の木質バイオマス導入事例
- 福島県の木質バイオマス導入事例
- 山形県の木質バイオマス導入事例
- 青森県の木質バイオマス導入事例
- 秋田県の木質バイオマス導入事例
- 香川県の木質バイオマス導入事例
- 徳島県の木質バイオマス導入事例
- 広島県の木質バイオマス導入事例
- 岡山県の木質バイオマス導入事例
- 鹿児島県の木質バイオマス導入事例
- 熊本県の木質バイオマス導入事例
- 愛媛県の木質バイオマス導入事例
- 大分県の木質バイオマス導入事例
- 長崎県の木質バイオマス導入事例
- 佐賀県の木質バイオマス導入事例
- 福岡県の木質バイオマス導入事例
- 岩手県の木質バイオマス導入事例
- 北海道の木質バイオマス導入事例
- 宮崎県の木質バイオマス導入事例
- 島根県の木質バイオマス導入事例
- 高知県の木質バイオマス導入事例
- 奈良県の木質バイオマス導入事例
- 福井県の木質バイオマス導入事例
- 東京都の木質バイオマス導入事例
- 取材協力・運営者情報
バイオマス発電とカーボンニュートラルの仕組み
バイオマス発電におけるカーボンニュートラルとはどのような考えでしょうか?環境を考えたカーボンニュートラルの仕組みを解説します。
カーボンニュートラルとは何?
バイオマス発電は、環境に優しい発電方法として知られています。その元になっているのは、カーボンニュートラルという考え方です。石油や石炭などの化学燃料を利用するのではなく、植物由来の資源を燃やして発電するのですが、発電の過程で発生した二酸化炭素は植物や自然を保つために循環できるというのがカーボンニュートラルです。 バイオマス発電で燃やしている材木は、元々大気中から樹木が吸収していた二酸化炭素を排出していると考えます。木材を燃やしているのですが、全体としての二酸化炭素は増えていないのです。また植物の成長に役立てることができるので、二酸化炭素のバランスが優れているのです。
カーボンニュートラルを目指すことのメリット
カーボンニュートラルを目指すことにはどのようなメリットがあるでしょうか?
まずは多くの発電施設で化石燃料が使われているので、大気汚染の軽減が見込まれます。化石燃料は限りがあるだけでなく、大気汚染の原因でもあります。しかしカーボンニュートラルを目指すことで、大気汚染や生態系のバランスを保たせる狙いもあるのです。
バイオマス発電でカーボンニュートラルを目指しているからと言って、ただバイオマス発電をするだけではいけません。ポイントとなるのは、バイオマス発電によって排出されている二酸化炭素と植物が吸収している二酸化炭素を同じスピードにするのです。
また別のポイントとして、地域の環境保全につながることもあります。そのために発電資源を作るための土地や他のバイオ燃料を使うことも大切です。各地域には未利用の間伐材がありますので、それらを利用することで、地域のカーボンニュートラルを実現できます。
しかし未利用の間伐材などが豊富にありますが、いつまでも伐採し続けることは不可能ですし、地域ごとに小規模でカーボンニュートラル発電を行えるようにすることや他のバイオ燃料の併用で、カーボンニュートラルを実現し環境保全につなげられるのです。
バイオマス発電のバイオマス資源の分類
生物由来のバイオマス資源として分類されているものには様々なものがあり、さらにバイオマス発電に用いられるバイオマス燃料にも複数の種類があります。
政府が定義するバイオマスの大まかな分類としては主として以下のようなものがあります。
- 廃棄物系資源:家畜排泄物・製材工場残材・食品廃棄物など
- 未利用資源:農作物・林地残材など
- 資源作物:なたね・デンプン系作物など
そしてそれらの中でもバイオマス発電の資源は固体燃料・液体燃料・気体燃料などに分けられることもポイントです。
- 固体燃料:木質燃料(間伐材・建築廃材・林地残材など)
- 液体燃料:バイオエタノール(サトウキビ・トウモロコシなど)
- 気体燃料:バイオガス(生ゴミ・家畜の糞尿など)
バイオマス燃料の分類
バイオマス燃料は、そのまま燃焼させて発電に用いる固体燃料の他にも、バイオマス由来のエタノールといった液体燃料や、生ゴミなどを発酵・ガス化させてメタンガスとして利用する気体燃料などに分類されます。
固体燃料
間伐材や廃材、あるいは可燃性のゴミといった燃焼可能なものは、燃焼性を高めた上で固体燃料としてバイオマス発電のエネルギー源に利用されます。
バイオマス燃料をそのまま燃焼させて水蒸気を発生させ、その力で蒸気タービンを使って発電する仕組みは直接燃焼方式と呼ばれ、石油や石炭を使う火力発電の代替エネルギーとして考えることができるでしょう。
固体燃料の燃焼性を高める方法としては木質ペレットや木質チップへの加工などがあります。
液体燃料
液体燃料として考えられるバイオマス燃料には、使用済みの菜種油やひまわり油といった植物油・廃油の他にもあります。トウモロコシやサトウキビといった農作物からアルコールを精製したバイオエタノールなど。また、その他にもミドリムシ(微細藻類ユーグレナ)のような藻類を活用して作られたバイオ燃料にも注目が集まっていることも無視できません。
バイオエタノールはバイオマス発電の燃料として利用されるだけでなく、バイオディーゼル燃料として石油の代替燃料にするといった活用法も期待されています。
気体燃料
生ゴミや家畜の糞尿、汚水などを発酵させてメタンガスのような燃焼ガスを発生させ、それを燃焼して発電する仕組みもあります。ガスタービンやガスエンジンを利用して発電する仕組みであり「生物化学的ガス化方式」と呼ばれる方法です。
それに対して木質ペレットや食品工場の廃棄物として出る野菜屑などを高温で熱処理し、ガス化させて用いる「熱分解ガス化方式」という発電方法も使われています。
バイオマス発電の導入にどんな課題・問題が考えられる?
環境負荷の軽減やエネルギー問題の解決に向けてバイオマス発電の導入を検討するとして、メリットだけでなく課題やリスクといったデメリットについて考えることも大切です。ここではバイオマス発電の導入に向けて考えるべき課題や問題として代表的なものを解説します。
主なバイオマス資源として木材に依存している
バイオマス発電に利用できるバイオマス資源としては、木質バイオマスだけでなく生ゴミや汚泥などから発酵させたバイオマスガスや、植物油・廃油といった液体バイオマス燃料なども考えられます。現実的にバイオマス発電の主なエネルギー源になっているものは木材を含む木質バイオマスが中心です。
言い換えれば国内のバイオマス発電は燃料である木材に依存していることが事実です。条件が限定されていることは解消すべき課題といえるでしょう。
バイオマス燃料の確保や生産・生成にコストと手間がかかる
バイオマス発電のメリットや目的として、再生可能エネルギーを利用してエネルギー資源の節約や二酸化炭素排出量の低減といったものが挙げられます。しかしそもそもバイオマス燃料を生成・生産するために労力やコストが必要なのが難点です。
現実的に、石油製品を利用して発電を行うよりも、バイオマス発電の方で圧倒的にコストや手間がかかる場合、生産性や効率が悪化してしまって持続困難になってしまうリスクが増えてしまいます。
そのためバイオマス燃料やバイオマス発電の効率化やエネルギー効率の向上には、バイオマス燃料の生産性を高める必要があります。
国内のバイオマス燃料需要の増加に伴って資源の輸入量が増加
日本国内で積極的にバイオマス資源の活用やバイオマス発電が進められていく中で、国内で用意できるバイオマス資源の量だけでは需要をまかなうことが難しいという問題もあります。
そのため、諸外国からバイオマス資源を輸入してバイオマス発電へ利用するという流れが生まれていますが、将来的に持続可能性を目指すためには資源を安定確保できる体制の構築が欠かせません。
バイオマス発電は本当にカーボンニュートラル?
バイオマス資源の活用やバイオマス発電は、カーボンニュートラルを推進して環境負荷の軽減に貢献し、持続可能な開発目標の達成も後押しするとされています。しかし、現実問題として莫大なコストや輸送用の燃料の消費と引き換えに海外からバイオマス資源を輸入している場合、そもそもトータルで見ればカーボンニュートラルを達成できません。
本当の意味でバイオマス発電による環境メリットを追及していくためには、現実を踏まえた上で二酸化炭素排出量や環境負荷の軽減を考え、全体でバランスを整えられるような仕組みを検討していくことが大切です。

https://www.bme.co.jp/wp/
木を選ばない
唯一無二のプラントを持つ
バイオマスエナジー社
木を原料に温風や水蒸気、バイオマスガスといった新たなエネルギーとしてリサイクルする画期的手法が、木質バイオマス。しかし、これまでバイオマスを燃やすプラントには燃料の制限があり、使いたい木材に対応できないというものばかりでした。
そうしたなかで、どんな木でも燃やせるプラントを誕生させたのが、バイオマスエナジー社です。当サイトでは、唯一無二のプラントを持つバイオマスエナジー社(2019年7月現在)に取材協力を依頼。実際にどんなプラントなのか、そしてコスト削減はどれくらいか。現地取材しレポートにまとめたので、ぜひご覧ください。