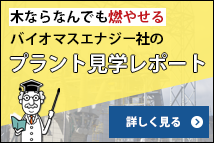sponsored by バイオマスエナジー社
- 木くずの再利用
- 木材のカスケード利用
- 製材を安定供給するために必要なこと
- 【特集】木材の最新リサイクル法 木質バイオマスとは
- 戻る
- 【特集】木材の最新リサイクル法 木質バイオマスとは_TOP
- 木質バイオマスのガイドラインとは?
- 小型木質バイオマス発電のメリット・デメリット
- バイオマスプラントとはどんな設備?
- バイオマス産業都市とは?
- 国内クレジット制度とは?バイオマス発電との関係も解説
- 木質バイオマス発電で発生する灰の処理方法
- バイオマス発電の
燃料調達方法・買取価格 - バイオマス発電の発電効率は?他の再生可能エネルギーと比較
- バイオマス発電事業を成功させるポイント
- バイオマス発電で想定されるトラブルとは
- バイオマス発電所の熱活用・熱利用
- 放射能汚染された木質燃料の危険性について
- 木質バイオマス発電は林業にとってプラスに働くのか?
- 地域活性化にはバイオマスが欠かせない?
- 森林経営管理制度とバイオマスの関係とは?
- 木質バイオマスの必要性とは
- バイオマス事業の将来性について
- 木質バイオマス利用施設に関連する補助金
- 小規模木質バイオマス発電の発電コストはどれくらい?
- 木質ガス化システムの仕組みとは?
- 直接燃焼発電とガス化発電の違いとは
- 木質バイオマスのメリット・デメリットとは
- 木くずが原因で起こった裁判
- バイオマス発電を事業化するには
- バイオマス発電の仕組みや特徴とは
- バイオマスボイラーを導入した場合のコスト
- バイオマスボイラー導入に関する注意点と法律
- 木質バイオマスの燃料
- 木質バイオマスの補助金
- 木質バイオマスの導入事例
- 木質バイオマスのプラント見学レポート
- 木質バイオマスのセミナー情報
- 木質バイオマスの失敗事例
- 木質バイオマス発電所の
保守・メンテナンス施策 - バイオマス発電の燃料を安定調達するために
- バイオマス用語集
- 木材リサイクル・バイオマスのコラムまとめ
- 戻る
- 木材リサイクル・バイオマスのコラムまとめ_TOP
- 産業廃棄物としての木くずの処理方法とは?
- クリーンウッド法とは?リサイクルとの関連性とは?
- リサイクルとアップサイクルの違いとは?
- 端材と廃材の違いとは?
- 脱炭素社会を目指す木材利用の可能性と課題について
- 木材利用によるCO2削減と
木質バイオマスとしての活用 - 産業廃棄物のリサイクルは必要?
どんなメリットがある? - 木材チップ・木質チップの含水率について知る
- 木質チップの品質規格について
- 廃棄物系バイオマスの利活用を考える
- ウッドプラスチックとは?廃木材のリサイクル事例について
- PCB廃棄物の木材の処理方法は?リサイクルはできる?
- 木質バイオマスにおける
固定価格買取(FIT買取 ) - 竹がバイオマス燃料に不向きな理由と近年の研究成果
- バイオマス発電投資をする前に考えるべきこと
- 価値を生む林地残材!
- 広い森林面積を持つ日本
- 産業廃棄物を処理するコストを削減するには
- エネルギー基本計画とは
- 固定価格買取制度(FIT制度)とは?
- 「地域内エコシステム」とは?
- バイオマス発電は輸入燃料頼み?人手不足の理由とは
- バイオマス発電でFITが見直しによりどうなるの?
- バイオマスビジネス参入するならどんな事業モデルがある?
- バイオマス発電とバイオガス発電の違いとは?
- バイオマス発電の魅力とは?
- エシカル消費ってなに?
- バイオマス発電とカーボンニュートラルの仕組み
- バイオマスとSDGs
- バイオマス活用推進基本計画とは?
- 木質バイオマスに使用されるボイラーの種類
- 木質バイオマス発電と熱電併給について
- 【エリア別】木質バイオマスの導入事例
- 戻る
- 【エリア別】木質バイオマスの導入事例_TOP
- 沖縄県の木質バイオマス導入事例
- 神奈川県の木質バイオマス導入事例
- 石川県の木質バイオマス導入事例
- 山口県の木質バイオマス導入事例
- 茨城県の木質バイオマス導入事例
- 宮城県の木質バイオマス導入事例
- 千葉県の木質バイオマス導入事例
- 埼玉県の木質バイオマス導入事例
- 兵庫県の木質バイオマス導入事例
- 滋賀県の木質バイオマス導入事例
- 大阪府の木質バイオマス導入事例
- 京都府の木質バイオマス導入事例
- 鳥取県の木質バイオマス導入事例
- 和歌山県の木質バイオマス導入事例
- 山梨県の木質バイオマス導入事例
- 群馬県の木質バイオマス導入事例
- 富山県の木質バイオマス導入事例
- 三重県の木質バイオマス導入事例
- 愛知県の木質バイオマス導入事例
- 新潟の木質バイオマス導入事例
- 静岡県の木質バイオマス導入事例
- 岐阜県の木質バイオマス導入事例
- 長野県の木質バイオマス導入事例
- 栃木の木質バイオマス導入事例
- 福島県の木質バイオマス導入事例
- 山形県の木質バイオマス導入事例
- 青森県の木質バイオマス導入事例
- 秋田県の木質バイオマス導入事例
- 香川県の木質バイオマス導入事例
- 徳島県の木質バイオマス導入事例
- 広島県の木質バイオマス導入事例
- 岡山県の木質バイオマス導入事例
- 鹿児島県の木質バイオマス導入事例
- 熊本県の木質バイオマス導入事例
- 愛媛県の木質バイオマス導入事例
- 大分県の木質バイオマス導入事例
- 長崎県の木質バイオマス導入事例
- 佐賀県の木質バイオマス導入事例
- 福岡県の木質バイオマス導入事例
- 岩手県の木質バイオマス導入事例
- 北海道の木質バイオマス導入事例
- 宮崎県の木質バイオマス導入事例
- 島根県の木質バイオマス導入事例
- 高知県の木質バイオマス導入事例
- 奈良県の木質バイオマス導入事例
- 福井県の木質バイオマス導入事例
- 東京都の木質バイオマス導入事例
- 取材協力・運営者情報
バイオマス発電を事業化するには
バイオマス発電の中でも、燃料として木材を利用する小規模発電を事業化する際に、おさえておきたいポイントをまとめています。小規模発電では、「売電」は難しいですが「売熱」は可能です。小規模ならでのメリットを生かしつつ、同時に利益を出すための方法を考えていきましょう。
採算性をふまえたバイオマス発電
コストをできる限り抑えることが、利益を出すためには必須です。
関連事業との連携
まず、安い価格で燃料を調達する方法を確保しましょう。そのためには、木材の確保のみならず、木材を燃料として使用可能な状態に加工する会社との連携、つまり「サプライチェーン」の構築が効果的です。連携の仕方にもよりますが、無駄のない物流システムを構築する・仲介業者に支払うマージンを抑えることなどができれば、コスト削減が可能になります。
需要や燃料についてリサーチ
また、小規模木質バイオマス発電を導入する地域の需要を、詳細に把握しておきましょう。たとえば、その地域で「どのくらいの規模の熱需要があるのか?」「需要が高いのは蒸気と温水のどちらなのか?」などです。事前リサーチが必要なのは、需要に応じて燃料として使う最適な木材の種類が変わってくるためです。また、特定の木材を地域内で調達できるのかどうかも確認しておかなければなりません。
もう一つ押さえておきたいポイントは、「熱の単価は一定」だということです。期間は決まっていますが、FIT制度により未利用木材を燃料として発電した電気の価格は、やや高めに設定されています。けれども、売熱にはそのルールは適用されません。地域で流通している木材の価格などをリサーチした上で、もっとも採算性が見込める木材を選択するべきなのです。
デマンドサイド(需要側)の視点に立つ
熱は、電気のようにFIT制度で価格が定められていないので、バイオマス発電事業者が熱の価格設定を行います。ですので、熱需要者と契約を結ぶ前に、燃料となる木材の市場価格変動リスクや熱供給先の脱退リスクなどを充分に計算した上で価格を設定しましょう。契約期間などについても、適切な条件を加えておくことが大切です。
地域活性化につながる事業形成
バイオマス発電を事業として成立させるためには、もちろん採算性を無視できません。ただ、採算性を確保しながら、同時に発電を行う地域の活性に繋がる体制の構築が理想的です。そのためにも、自治体の役割が今後より一層重要になります。地域の経済が活性化すれば、熱需要の増加が予想されるため、当然、バイオマス発電事業の収益増加が見込まれます。
バイオマス発電事業の意義について、事業者協会では「ベースロード電源エネルギー(天候などに左右されることなく、一定量の電力を安定的に供給できる電源)」あるいは「温室効果ガスである二酸化炭素の排出量を削減する発電」などと定めています。バイオマス発電は、社会や地球環境に貢献する役割を担った事業のひとつである位置づけなのです。

https://www.bme.co.jp/wp/
木を選ばない
唯一無二のプラントを持つ
バイオマスエナジー社
木を原料に温風や水蒸気、バイオマスガスといった新たなエネルギーとしてリサイクルする画期的手法が、木質バイオマス。しかし、これまでバイオマスを燃やすプラントには燃料の制限があり、使いたい木材に対応できないというものばかりでした。
そうしたなかで、どんな木でも燃やせるプラントを誕生させたのが、バイオマスエナジー社です。当サイトでは、唯一無二のプラントを持つバイオマスエナジー社(2019年7月現在)に取材協力を依頼。実際にどんなプラントなのか、そしてコスト削減はどれくらいか。現地取材しレポートにまとめたので、ぜひご覧ください。