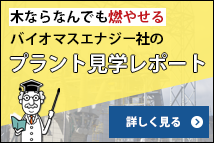sponsored by バイオマスエナジー社
- 木くずの再利用
- 木材のカスケード利用
- 製材を安定供給するために必要なこと
- 【特集】木材の最新リサイクル法 木質バイオマスとは
- 戻る
- 【特集】木材の最新リサイクル法 木質バイオマスとは_TOP
- 木質バイオマスのガイドラインとは?
- 小型木質バイオマス発電のメリット・デメリット
- バイオマスプラントとはどんな設備?
- バイオマス産業都市とは?
- 国内クレジット制度とは?バイオマス発電との関係も解説
- 木質バイオマス発電で発生する灰の処理方法
- バイオマス発電の
燃料調達方法・買取価格 - バイオマス発電の発電効率は?他の再生可能エネルギーと比較
- バイオマス発電事業を成功させるポイント
- バイオマス発電で想定されるトラブルとは
- バイオマス発電所の熱活用・熱利用
- 放射能汚染された木質燃料の危険性について
- 木質バイオマス発電は林業にとってプラスに働くのか?
- 地域活性化にはバイオマスが欠かせない?
- 森林経営管理制度とバイオマスの関係とは?
- 木質バイオマスの必要性とは
- バイオマス事業の将来性について
- 木質バイオマス利用施設に関連する補助金
- 小規模木質バイオマス発電の発電コストはどれくらい?
- 木質ガス化システムの仕組みとは?
- 直接燃焼発電とガス化発電の違いとは
- 木質バイオマスのメリット・デメリットとは
- 木くずが原因で起こった裁判
- バイオマス発電を事業化するには
- バイオマス発電の仕組みや特徴とは
- バイオマスボイラーを導入した場合のコスト
- バイオマスボイラー導入に関する注意点と法律
- 木質バイオマスの燃料
- 木質バイオマスの補助金
- 木質バイオマスの導入事例
- 木質バイオマスのプラント見学レポート
- 木質バイオマスのセミナー情報
- 木質バイオマスの失敗事例
- 木質バイオマス発電所の
保守・メンテナンス施策 - バイオマス発電の燃料を安定調達するために
- バイオマス用語集
- 木材リサイクル・バイオマスのコラムまとめ
- 戻る
- 木材リサイクル・バイオマスのコラムまとめ_TOP
- 産業廃棄物としての木くずの処理方法とは?
- クリーンウッド法とは?リサイクルとの関連性とは?
- リサイクルとアップサイクルの違いとは?
- 端材と廃材の違いとは?
- 脱炭素社会を目指す木材利用の可能性と課題について
- 木材利用によるCO2削減と
木質バイオマスとしての活用 - 産業廃棄物のリサイクルは必要?
どんなメリットがある? - 木材チップ・木質チップの含水率について知る
- 木質チップの品質規格について
- 廃棄物系バイオマスの利活用を考える
- ウッドプラスチックとは?廃木材のリサイクル事例について
- PCB廃棄物の木材の処理方法は?リサイクルはできる?
- 木質バイオマスにおける
固定価格買取(FIT買取 ) - 竹がバイオマス燃料に不向きな理由と近年の研究成果
- バイオマス発電投資をする前に考えるべきこと
- 価値を生む林地残材!
- 広い森林面積を持つ日本
- 産業廃棄物を処理するコストを削減するには
- エネルギー基本計画とは
- 固定価格買取制度(FIT制度)とは?
- 「地域内エコシステム」とは?
- バイオマス発電は輸入燃料頼み?人手不足の理由とは
- バイオマス発電でFITが見直しによりどうなるの?
- バイオマスビジネス参入するならどんな事業モデルがある?
- バイオマス発電とバイオガス発電の違いとは?
- バイオマス発電の魅力とは?
- エシカル消費ってなに?
- バイオマス発電とカーボンニュートラルの仕組み
- バイオマスとSDGs
- バイオマス活用推進基本計画とは?
- 木質バイオマスに使用されるボイラーの種類
- 木質バイオマス発電と熱電併給について
- 【エリア別】木質バイオマスの導入事例
- 戻る
- 【エリア別】木質バイオマスの導入事例_TOP
- 沖縄県の木質バイオマス導入事例
- 神奈川県の木質バイオマス導入事例
- 石川県の木質バイオマス導入事例
- 山口県の木質バイオマス導入事例
- 茨城県の木質バイオマス導入事例
- 宮城県の木質バイオマス導入事例
- 千葉県の木質バイオマス導入事例
- 埼玉県の木質バイオマス導入事例
- 兵庫県の木質バイオマス導入事例
- 滋賀県の木質バイオマス導入事例
- 大阪府の木質バイオマス導入事例
- 京都府の木質バイオマス導入事例
- 鳥取県の木質バイオマス導入事例
- 和歌山県の木質バイオマス導入事例
- 山梨県の木質バイオマス導入事例
- 群馬県の木質バイオマス導入事例
- 富山県の木質バイオマス導入事例
- 三重県の木質バイオマス導入事例
- 愛知県の木質バイオマス導入事例
- 新潟の木質バイオマス導入事例
- 静岡県の木質バイオマス導入事例
- 岐阜県の木質バイオマス導入事例
- 長野県の木質バイオマス導入事例
- 栃木の木質バイオマス導入事例
- 福島県の木質バイオマス導入事例
- 山形県の木質バイオマス導入事例
- 青森県の木質バイオマス導入事例
- 秋田県の木質バイオマス導入事例
- 香川県の木質バイオマス導入事例
- 徳島県の木質バイオマス導入事例
- 広島県の木質バイオマス導入事例
- 岡山県の木質バイオマス導入事例
- 鹿児島県の木質バイオマス導入事例
- 熊本県の木質バイオマス導入事例
- 愛媛県の木質バイオマス導入事例
- 大分県の木質バイオマス導入事例
- 長崎県の木質バイオマス導入事例
- 佐賀県の木質バイオマス導入事例
- 福岡県の木質バイオマス導入事例
- 岩手県の木質バイオマス導入事例
- 北海道の木質バイオマス導入事例
- 宮崎県の木質バイオマス導入事例
- 島根県の木質バイオマス導入事例
- 高知県の木質バイオマス導入事例
- 奈良県の木質バイオマス導入事例
- 福井県の木質バイオマス導入事例
- 東京都の木質バイオマス導入事例
- 取材協力・運営者情報
建築廃材
燃料だけでなくプラスチックや紙、コンクリートなどにリサイクルされる建築廃材について、再利用方法や再利用事例を紹介します。

建築廃材の主な再利用方法
製紙用チップ
建築廃材などで未使用のものやそれに近しい建築廃材は、製紙用チップに生まれ変わる可能性があります。針葉樹や広葉樹から抽出されます。トイレットペーパーなど生活に欠かせない日用品の一部となっているわけです。
とはいえ、紙パルプ産業の需要落ち込みもあり、製紙用チップの数は低下しています。
RPF燃料
RPFとはRefuse Paper & Plastic Fuelの略で、固形燃料のことです。化石燃料の代替として注目され、コストやCO2の低減に寄与しています。
需要推移は2016年まで右肩上がりでしたが、2017年度に需要が30万t落ちて140万tになっています。
参照元:日本RPF工業会(http://www.jrpf.gr.jp/rpf-6)
セメント原燃料
セメント産業では多くの廃棄物を受け入れているケースが多く、そのひとつが建築廃材です。近年は建築廃材や下水汚泥の使用量が増加しており、需要は高いと言えるでしょう。
バイオマス燃料
建築廃材の大部分を占めるのが木材で、これを再利用するのがバイオマス燃料となる木質チップ。木材を燃えやすいチップ状にすることで、ボイラーや発電機などの燃料として使われ、排熱や電力として再利用。CO2排出量や化石燃料の削減にも役立っています。
建築廃材の再利用の現状
建築廃材は主に住宅を解体した際に出る廃材を意味します。厳密にいえば住宅を建てる際にも加工などに伴う廃材が出ますが、建築廃材という場合、ほぼ住宅解体材と考えてもいいでしょう。
日本は木造住宅が多いこともあり、廃材もやはり木材がもっとも多くなります。これらは木材チップに、基礎などで使われていたコンクリートは砕石に、そして鉄や金物などは処理施設で磁石によって除去されるといった流れで再利用されます。
なお、土木系廃棄物はリサイクル率が70%近いのに対して、建築系廃棄物は同42%と、まだまだ再利用が十分ではないともいえます。
参照元:建築廃棄物の現状(https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/pdf/recyclehou/hourei_kokuji/data_02.pdf)
建築廃材の再利用事例
燃焼効率増
バイオマス導入の経緯
- 加工残材の有効利用のため
活用している木の燃料
- おが粉、加工残材など
導入の成果
- メンテナンス費を年間100万円削減、燃料効率が50%から75%に上昇
詳細を見る
岐阜県高山市にあるシラカワという木製家具メーカーで、製造工程に木屑焚きボイラーを活用している事例を紹介します。
木製家具メーカーは、製品を製造する工程でどうしても木屑やおが屑を出してしまいます。それをバイオマス燃料として再利用するのが主たる目的です。
シラカワの工場では日々1~2t、年間で約500tにもなる木屑が出ますが、すべてをリサイクル。蒸気式から煙管水管組み合わせ式木屑焚きボイラーを導入することで、工場やオフィスの暖房や木製家具の乾燥・加熱などに利用しています。木屑自体は完全燃焼して灰となりますが、これらも肥料や土地改良材として再利用。
この事例では、30年ほど使っていた木屑焚きボイラーを最新化することで、メンテナンス費を年間100万円削減するとともに、蒸気の不安定さから脱却。さらに燃焼効率が50%から75%に向上するなど、大きな効果を得ています。
参照元:新エネルギー・産業技術総合開発機構(https://www.nedo.go.jp/content/100859993.pdf)
温泉の加温に活用
バイオマス導入の経緯
- 交付税の削減、農林産物の価格低迷
活用している木の燃料
- チップ
導入の成果
- 燃料費削減効果は、年間2,500万円
詳細を見る
北海道上川郡にある五味温泉という温泉宿泊施設では、それまで使っていた重油ボイラーを2005年度からチップボイラーに切り替えて、給湯や暖房、温泉の加温に活用しています。
燃料として使っているのは、集成材を加工する際にできてしまう端材。これは未利用の木材ではありますが、そのままだと産業廃棄物となってしまうところ、バイオマス燃料として再利用しているわけです。
この端材を燃料チップに加工して年間300tを活用し、バイオマスボイラー導入から7年間で2,500万円の燃料費削減となっています。
参照元:林野庁(http://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/biomass/pdf/250610biomass5.pdf)
好影響も多数
バイオマス導入の経緯
- 未利用材の再利用
活用している木の燃料
- 端材、スギ樹皮など
導入の成果
- 松食い材のエネルギー利用、設備更新費の節約、雇用の拡大
詳細を見る
秋田県は森林資源が豊富で、スギを中心として年間80万㎥もの木材を取り扱っています。そのぶん、樹皮や端材などが廃材となっていて、そのボリュームは木材全体の8~10%ほど。県内でも木材加工業者がもっとも多い能代市で、能代森林資源利用協同組合が廃材を再利用してバイオマス発電を行なっている事例を紹介します。
樹皮や端材などはすべてを廃棄していたわけではなく、一部は堆肥として再利用していましたが、能代森林資源利用協同組合による取り組みはバイオマス発電の燃料と木質ボードの原料として廃材を再利用するもの。発電した電気は電力会社に販売したり、木質ボート製造工場に供給してもいます。
廃材の有効活用により焼却炉の設備更新の必要がなくなったうえ、松食い材の処理が可能に。そのほか、地域での木質廃材の不法投棄や、加工業者による焼却設備の買い替えの必要がなくなったなど、森林資源のリサイクル以外にも好影響が見受けられます。
参照元:農林水産省(http://www.maff.go.jp/j/nousin/tiiki/sanson/img/pdf/tokusyuu_4-1_part1.pdf)
そもそも建築廃材はリサイクルが義務?
法律で義務付けられているリサイクル
かつては解体の際に生じた廃材はゴミとしての扱いになっていました。しかし、昨今は地球環境への配慮から、廃材をリサイクルするよう、法律でも定められています。さまざまな再資源化がどの程度行われているかについての実態調査の結果も出ています。
特に木材についての調査結果は、85%から90%というかなりの高い数字がでてるようです。リサイクルは、やはり確実に時代の潮流となっていることがうかがえます。ただし、環境に良いからと勝手に処理をしてしまうのはNG.というのも、廃材の処理の仕方をまちがって、法律違反となってしまうためです。不安な場合は、自宅を解体する際などは、専門家やリサイクル業者に相談してみましょう。
解体工事に依頼した場合も再利用している
解体業者に解体を依頼する人も多いと思われますが、業者もリサイクル法を守る必要があります。そのため、たとえば自宅を解体した際に発生した廃材の処理を解体業者にあわせて依頼した場合も、廃材のほとんど全ては何らかの形でリサイクルされているのが実情です。
プロセスとしては、廃材や廃棄物を品目ごとに分けてトラックなどに搭載し、それを中間処理業者でさらに多くの種類に分別するよう依頼するのが一般的です。中間処理業者では、分別したものをさらにチップやペレットなどに加工します。これで、リサイクルとして成立しているのです。
業者に任せた方がコストを抑えられることもあるけれど
上述したように、中間処理業者は廃材を最終的にチップなどに加工します。加工した製品を販売することで得られる収入を利益の一部としています。そのため、解体業者が中間処理業者に支払う処理費用がその分安くなっています。また、思い出のつまった自宅の廃材をとっておいて、新しく建てる家の柱などに利用できないかな、と考える人もいるかもしれません。その場合は、木材にできるかぎりダメージを与えずに解体作業を行わなくてはならないので、注意が必要です。当然コストがあがることを計算しておく必要があります。
また、新しい家の建材として利用するまでしなくとも、廃材を自分でウッドチップにしたい、と考える人もいるかもしれません。けれども、その場合は投手な機械が必要ですし、さらに異物を取り除くなど、予想以上に多くの手間がかかってしまいます。コストもそうとうかかってしまいます。プロに任せるのがやはりおすすめです。
様々なコストがかかるので、自社で解体・廃棄をするよりも業者に任せたほうが基本的には安上がりです。しかし、それでも安くはない費用はかかってしまいます。
建築廃材の種類別に見る再利用・リサイクル方法
建築現場では多種多様な材料が使用されますが、それらの多くが建築廃材として終わるだけでなく、リサイクルや再利用の方法が模索されています。この取り組みは、環境保護だけでなく、経済的にも効果的であり、サステナビリティへの大きな一歩を意味しています。リサイクルプロセスを通じて、廃材は新たな資源として再生され、持続可能な社会の構築に貢献。建築廃材の主要な種類ごとに、その再利用やリサイクルの具体的な方法を見ていきましょう。
木材・木くず
建築現場で出る木材や木くずは、リサイクルが比較的容易な材料です。これらは主にチップ化されて、新たな木製品の製造やエネルギー源として活用されます。バイオマス燃料としての利用が注目されており、エネルギー回収としての価値も高いです。また、木材の廃材は、家具や建材など、さまざまな製品の原料としても再利用されています。
コンクリート
解体されたコンクリートは、再生砕石として再利用される傾向にあります。この砕石は新しい建築材料や公共工事の道路基盤として利用され、廃材を有効活用する方法として広く取り入れられています。また、これにより廃棄物の処理コストを削減し、環境への負担を軽減が可能です。
石膏ボード類
建築内装で使用される石膏ボードは、解体後にリサイクルが可能です。粉砕された石膏ボードは、新しい石膏ボードの生産原料や土壌改良材として再利用されることがあります。これにより、建築廃材から有価物を生み出し、廃棄量の削減に貢献しています。
プラスチック
プラスチック廃材は、リサイクルして新たなプラスチック製品を製造することが一般的です。また、固形燃料として利用されることもあり、廃材から新たなエネルギー源を創出しています。これは、環境負荷の低減と資源の有効活用を可能にします。
ガラス類
解体されたガラスは、再生して新しいガラス製品の材料として利用されるほか、建築材料としても再利用されます。ガラスのリサイクルにより、資源の無駄を大きく削減し、環境保護に寄与しています。
金属類
金属廃材は、建築業界において重要なリサイクル材料のひとつとなっています。そのため、ほぼ100%が再利用されており、解体現場から回収された金属は種類ごとに分類され、精製プロセスを経て新たな建材や機械部品などに再生されます。この工程を踏むことで資源の循環を促進し、廃材の有効活用が進められるのです。
建築廃材の再利用におすすめは、木質バイオマス
建築廃材を再利用する際、もっとも効率的なのが木質バイオマスと言えるでしょう。導入事例からも見えるとおり、化石燃料からのコスト削減、CO2抑制など、メリットは少なくありません。
木質バイオマスのプラントを導入するうえで注目すべきは、建築廃材すべてに対応できる製品かどうか。そこが見合っていないと原料の調達コストがかかるうえ、対応していない原料が混入すると機械がストップしてしまう可能性があります。
そうしたなかで、建築廃材すべてを燃やせるプラントを開発した企業がいます。それが、バイオマスエナジー社です。

https://www.bme.co.jp/wp/
木を選ばない
唯一無二のプラントを持つ
バイオマスエナジー社
木を原料に温風や水蒸気、バイオマスガスといった新たなエネルギーとしてリサイクルする画期的手法が、木質バイオマス。しかし、これまでバイオマスを燃やすプラントには燃料の制限があり、使いたい木材に対応できないというものばかりでした。
そうしたなかで、どんな木でも燃やせるプラントを誕生させたのが、バイオマスエナジー社です。当サイトでは、唯一無二のプラントを持つバイオマスエナジー社(2019年7月現在)に取材協力を依頼。実際にどんなプラントなのか、そしてコスト削減はどれくらいか。現地取材しレポートにまとめたので、ぜひご覧ください。